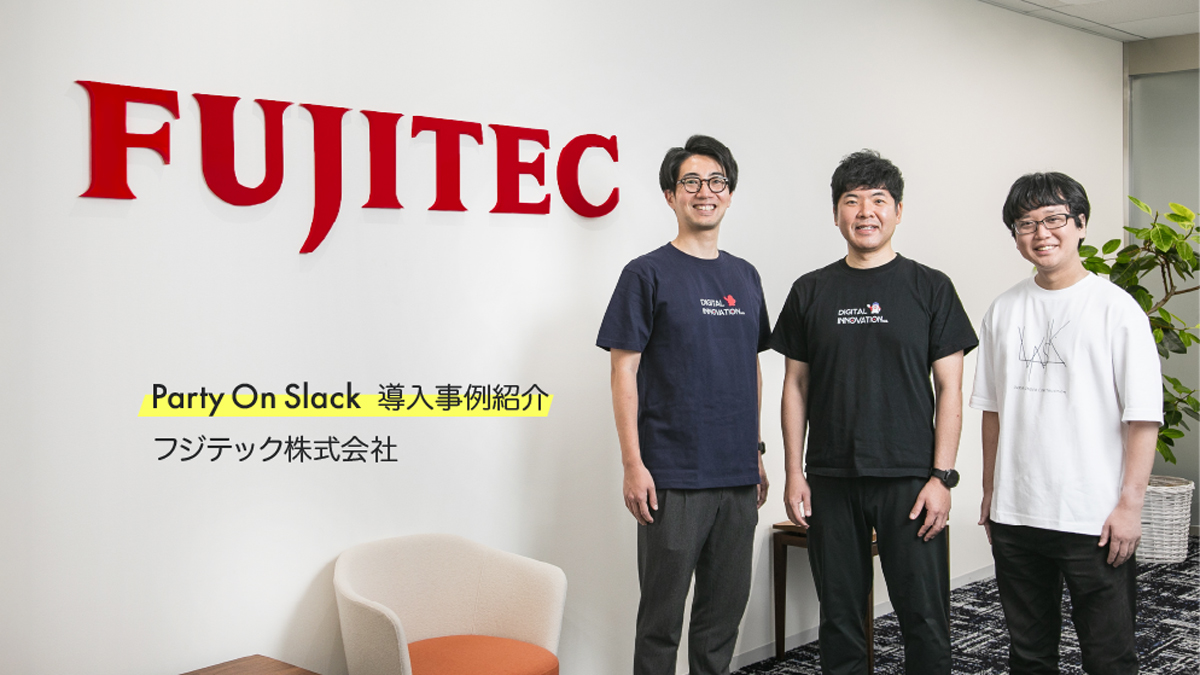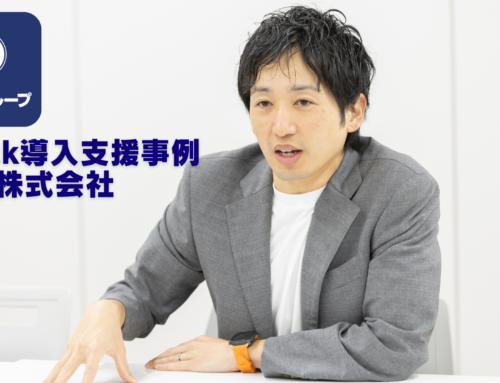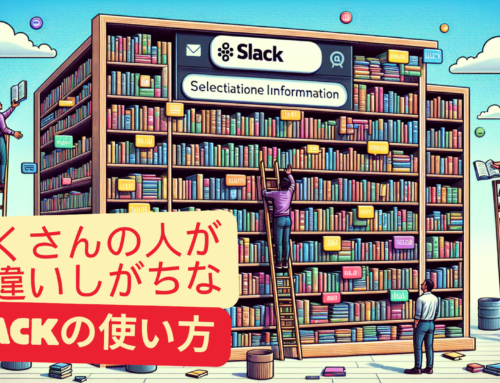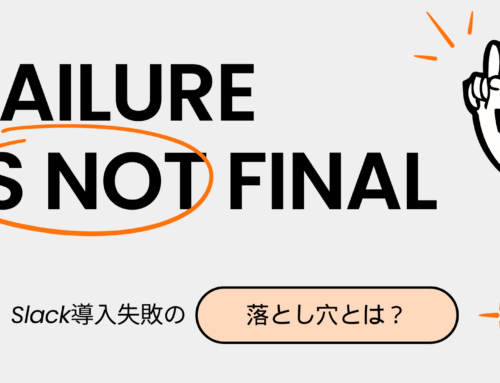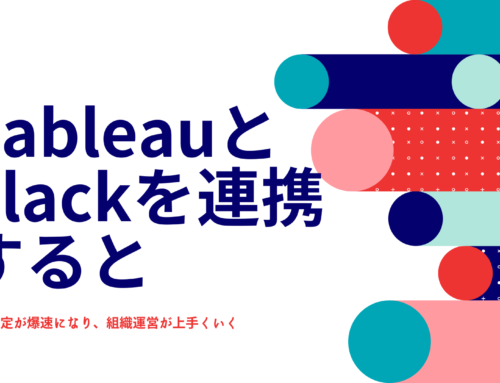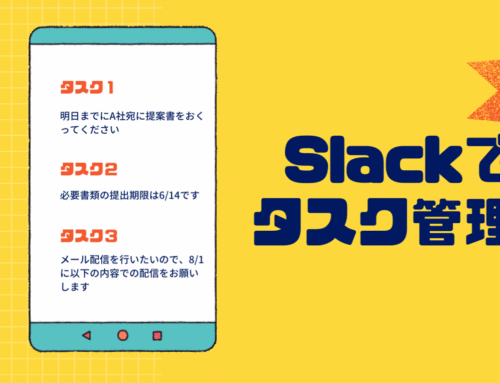Project Description
エレベータやエスカレータ、動く歩道など都市空間移動システムを専門に手掛けるフジテック株式会社は、2023年5月、全社員向けに「Party on Slack」を導入した。Slack上でChatGPTやGemini、Claudeなど複数の生成AIモデルを利用できるアプリを活用することで、研究・開発・販売・製造・保守・リニューアルなど多様な現場の生産性向上を狙う。
導入から2年、社内には「まずはAIに聞いてみよう」という文化が芽生え、生産性が向上。DX化を推進する友岡賢二専務執行役員 デジタルイノベーション本部長は、「2024年には年間31,796時間もの“時間創出効果”が見込まれた」と語る。導入から普及までを担ってきた担当の佐竹氏と小畑氏、そして「Party on Slack」を開発してきた弊社 古泉が舞台裏を語り合った。
「創造的ワークを行えるプラットフォーム」を手に入れる
―Party on Slackのリリースからほどなく導入を決められました。
佐竹 2023年3月にChatGPT-4が登場し、「これはすごいものが出た!」と巷でも盛り上がりましたよね。その時期に社内でも本格的に生成AI活用を検討しました。AI活用が必須になっていくことは予想されましたが、社員が個別にAIを使い始めれば、情報管理はバラバラになり、セキュリティリスクも生じます。そこで出会ったのが「Party on Slack」でした。3月に検討を開始し、5月15日には全社公開と、かなりのスピード感で進めました。

フジテック株式会社
デジタルイノベーション本部
システム管理部長 兼
情報セキュリティ統括室 主幹
佐竹 右教 氏
古泉 開発者としてありがたい限りです。
―決め手は何だったのでしょう。
佐竹「スピード・コスト・安全・ナレッジ共有」の4要素がそろっていたことです。無料版を素早く導入できることに加え、API経由でAIとやり取りをするため、OpenAI側に学習されたり、情報が流出したりするリスクを抑えられることが、魅力でした。
―御社ではSlackの全社導入も初だったため、大変なこともあったのでないかと思います。Slack×AIの同時導入に踏み切った理由は何でしょうか。
佐竹 Slackを介さずに、Webブラウザー上で個別にAIを使う方法もありました。ただ、それでは「AIと自分だけ」の閉じられた世界になってしまいます。「Party on Slack」の利点は、「仲間・AI・自分」の三者のやり取りができるところです。つまり、社内の問題を可視化し、解決策を共有することができるのです。
単なるAI活用だけでもなく、かといってコミュニケーションツールにもとどまらない。「Party on Slack」の導入で、グループ全体が「創造的ワークを行えるプラットフォーム」を手に入れられる。これが最大の価値でした。
社内を巻き込む〝伝道師戦略〟
―導入から2年が経ち、現在の浸透率はどれくらいですか?
佐竹 全社約3500人中、現在、1200人強が日常業務で活用しています。もっともここに至るまでは紆余曲折もありました。当初、「Party on Slack」導入の発表と同時に利用希望者を募ったところ、約520名から申し込みがありました。
古泉 そんなに多くの申し込みがあったんですね。モノづくりの現場では、ノウハウなどの情報共有や蓄積が大切だと思いますが、順調に活用していただいたのでしょうか。
佐竹 スタートダッシュとしては順調だったのですが、いざ始まってみると、活用率がどんどん低下して、約半分になってしまいました。そこで全社アンケートを実施したところ、およそ8割の社員が「全然使っていない」または「週に1,2回程度しか使わない」という残念な回答でした。さらに理由を尋ねると「どこで活用したらいいか分からない」「どんなプロンプトを入力すればいいのか分からない」「そもそもAIで何ができるのか分からない」という答えが並びました。
―興味関心はあるものの、実際の使い方で戸惑いを感じていたということでしょうか。
佐竹 はい。そのため、活用に向けたオンラインセミナーを実施することにしたんです。全12回実施し、延べ1036名が参加してくれました。セミナーでは、社内で特に「Party on Slack」を使い倒している熱量の高い社員を見つけ出し、講師役になってもらいました。「営業現場ではこんな使い方をしている」「設計では……」「広報では……」などの現場でのリアルな使用例を語ってもらいました。
加えて、全国の拠点に赴き、リアルな講習会も実施しました。PCをあまり触らない業務に従事している社員にもPCの前に座ってもらい、Slackの意義や生成AIには何ができるのかをレクチャーしたんです。すると最初は戸惑っていた人たちも、講習会を終える頃には「これ、すごい!」と好反応で(笑)。どんどん口コミでも広まっていきました。
小畑 日頃PC業務に慣れているバックオフィス社員からも、「AIの使い方が分からない」「そもそもSlackの使い方が分からない」という声は結構ありました。小さな相談も気軽に発せられる環境を整えたり、社内瓦版を発行するなど、あの手この手で周知・普及をジワジワと進めていきました。
―導入からある程度の定着まで、時間的にはどれくらいかかりましたか。
佐竹 ひと通りの普及施策に1年半ほどかかりましたが、やはり新システム導入には、最初に「ゼロイチの機会」をしっかりつくるべきだと実感しました。というのも皆、特にAIを使わなくても、日々の業務で特に困っているわけではないのです。そんな中「『Party on Slack』を使えば仕事の効率が上がりますよ」と力説してもイメージがわかない。サービスやシステムの価値を納得してもらうためには、やはり「体感」が必要だということです。
―定着したいま、御社内では実際にどのような使われ方をしていますか?
小畑 例えば広報部門では、対外的文書の表記の揺れチェックやブランディングのアイデア出しの壁打ちによく使われています。研究部門では複雑な計算やシミュレーションを行う際、従来はエクセルに膨大な関数を入れて計算していましたが、まずは生成AIに投げ込んでみるようになりました。また、営業部門では、取引先へのメール文面をどの程度、丁寧にするべきかの塩梅を確認し、「そこまで慇懃でなくていいですよ」とAIから提案されたり(笑)、本当に日常的に使っていますね。
自分の悩みは、他者の課題でもあります。皆が陥りがちな課題を社内共有のプロンプト集としてまとめたり、誰もが使えるTips化したり。社内文化として「まずはAIに聞いてみよう」が浸透していったのは、とても良い傾向だと思っています。

フジテック株式会社
デジタルイノベーション本部
プロセス管理部 主務
小畑 俊介氏
―セミナー開催など周知・普及活動を続けた成果ですね。
佐竹 はい。ただ、それだけでなく、当社では2024年の5月に中期経営計画「Move On 5」を発表し、その中で「生成AI活用によるルーティンの効率化」を掲げました。要するに会社から「生成AIを業務に使うべし」というお墨付きを得た。実はこれも重要だったと思っています。
生成AIに関しては、いまだ利用者側に温度差があります。すでに日常業務で駆使している人がいる反面、人によっては、いまだに生成AIを業務で利用する事に抵抗がある方もいらっしゃいます。実際に当社でも「業務中にSlackを使ってもいいのでしょうか」という質問が来たこともあります(笑)。
新システムは導入時こそ盛り上がりますが、普及には時間がかかり、成果はすぐには表れません。その間に熱が冷めてしまうこともあります。社内のことを熟知し、新システム導入の意義を理解している〝熱量の高い人物〟を中心にチームを組み、常にアップデートし続けること、「社内の熱量を灯し続ける」ことが大切だと思います。
3万時間超の時間創出。未来の働き方をつくりたい
―「Party on Slack」導入による効果について教えてください。「年間3万時間以上の時間が創出された」という御社デジタルイノベーション本部長の発言もありました。
佐竹 特に汎用的な算出式があるわけではないと思いますが、AIとのやり取りの回数と、それにより何分の時間短縮につながったかという独自のロジックで算出した数字です。
古泉 業務内容によっても算出方法は異なりますよね。ただ、例えば私も取引先へメールを送る際、文面を作成・校正すると10分程度はかかります。それがAI活用で60秒に圧縮できれば、単純計算で1件当たり9分の削減になります。そうした事例に基づき、算出しているのだと思います。
―これだけの時間が創出されると、働き方そのものが変わってきますね。
佐竹 まさにおっしゃる通りで、AI活用で日々の雑務や困りごとに頭を悩ましていた時間を圧縮できれば、浮いた時間をそれぞれの仕事の質向上に費やすこともできますし、本来やりたかったことに集中もできる。労働時間の短縮につながるかもしれません。「『Party on Slack』を使うこと」で、毎日の仕事へのワクワク感が増す。大げさでなく、そんな働き方も実現するのではと思います。
―今後、「Party on Slack」に期待することを教えてください。
小畑 現在は、ユーザー側が積極的に要望をAIに伝えていますが、将来的には生成AI自ら、「いま~した方がいいですよ」とか「~を確認してください」と提案してくれるような、より対話的な形になってくれることを期待します。「『Party on Slack』を使う」のではなく、「『Party on Slack』が協働パートナーになってくれる」、そんなイメージです。
佐竹 生成AI自体、どんどん進化していますよね。音声の文字起こし精度や、画像生成、AIアシスタント機能など。効率性や時間圧縮はますます進んでいくでしょう。その点、早い段階で「Party on Slack」を導入できたおかげで、「生成AIの成長」と、「当社のAI習熟度」が連動して伸びている実感があります。すでにSlack上には膨大なナレッジが集積しつつあり、やがてはSlack上で全ての業務が回る、〝Slackを中心としたエコシステム〟が実現するのではないかと期待しています。
究極的な理想は、AIがすべての量的判断やレコメンドを行い、人間は最終的な意思決定のみを担う世界です。しかしそこでは人との協働もちゃんとある。そんな世界観において、「Party on Slack」は欠かせないツールになっていきます。今後も期待しています。
古泉 開発側として、想定以上に熱意をもって使いこなしてくださっており、うれしいです。「Party on Slack」自体は、誰でも使える設計ですが、さらに「こうしたい」「あれができれば」というご要望があれば、今後もしっかり向き合っていきたいと思っています。

株式会社リバネスナレッジ
古泉 賢人

取材協力:フジテック株式会社
〒522-8588 滋賀県彦根市宮田町591-1