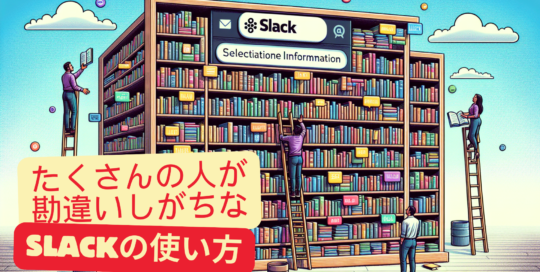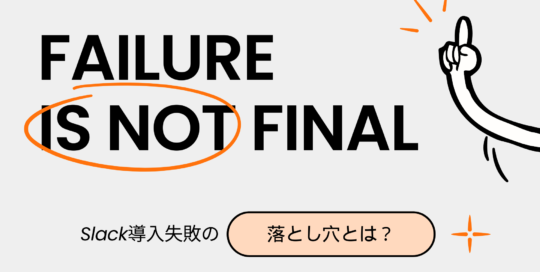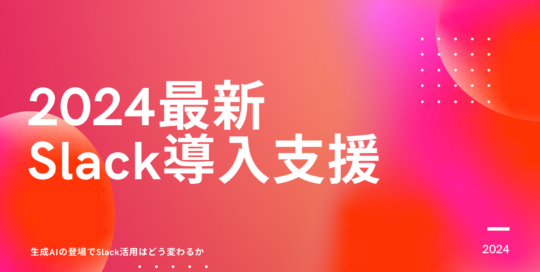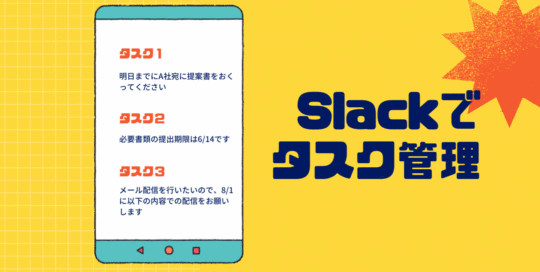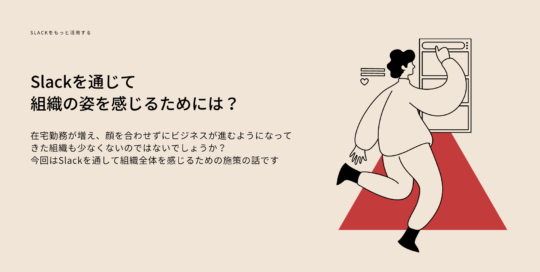エレベータやエスカレータ、動く歩道など都市空間移動システムを専門に手掛けるフジテック株式会社は、2023年5月、全社員向けに「Party on Slack」を導入した。Slack上でChatGPTやGemini、Claudeなど複数の生成AIモデルを利用できるアプリを活用することで、研究・開発・販売・製造・保守・リニューアルなど多様な現場の生産性向上を狙う。 導入から2年、社内には「まずはAIに聞いてみよう」という文化が芽生え、生産性が向上。DX化を推進する友岡賢二専務執行役員 デジタルイノベーション本部長は、「2024年には年間31,796時間もの“時間創出効果”が見込まれた」と語る。導入から普及までを担ってきた担当の佐竹氏と小畑氏、そして「Party on Slack」を開発してきた弊社 古泉が舞台裏を語り合った。 「創造的ワークを行えるプラットフォーム」を手に入れる ―Party on Slackのリリースからほどなく導入を決められました。 佐竹 2023年3月にChatGPT-4が登場し、「これはすごいものが出た!」と巷でも盛り上がりましたよね。その時期に社内でも本格的に生成AI活用を検討しました。AI活用が必須になっていくことは予想されましたが、社員が個別にAIを使い始めれば、情報管理はバラバラになり、セキュリティリスクも生じます。そこで出会ったのが「Party on Slack」でした。3月に検討を開始し、5月15日には全社公開と、かなりのスピード感で進めました。 フジテック株式会社 デジタルイノベーション本部 システム管理部長 兼 情報セキュリティ統括室 主幹 佐竹 右教 氏 古泉 開発者としてありがたい限りです。 ―決め手は何だったのでしょう。 佐竹「スピード・コスト・安全・ナレッジ共有」の4要素がそろっていたことです。無料版を素早く導入できることに加え、API経由でAIとやり取りをするため、OpenAI側に学習されたり、情報が流出したりするリスクを抑えられることが、魅力でした。 ―御社ではSlackの全社導入も初だったため、大変なこともあったのでないかと思います。Slack×AIの同時導入に踏み切った理由は何でしょうか。 佐竹 Slackを介さずに、Webブラウザー上で個別にAIを使う方法もありました。ただ、それでは「AIと自分だけ」の閉じられた世界になってしまいます。「Party on Slack」の利点は、「仲間・AI・自分」の三者のやり取りができるところです。つまり、社内の問題を可視化し、解決策を共有することができるのです。 単なるAI活用だけでもなく、かといってコミュニケーションツールにもとどまらない。「Party on Slack」の導入で、グループ全体が「創造的ワークを行えるプラットフォーム」を手に入れられる。これが最大の価値でした。 社内を巻き込む〝伝道師戦略〟 ―導入から2年が経ち、現在の浸透率はどれくらいですか? 佐竹 全社約3500人中、現在、1200人強が日常業務で活用しています。もっともここに至るまでは紆余曲折もありました。当初、「Party on Slack」導入の発表と同時に利用希望者を募ったところ、約520名から申し込みがありました。 古泉 そんなに多くの申し込みがあったんですね。モノづくりの現場では、ノウハウなどの情報共有や蓄積が大切だと思いますが、順調に活用していただいたのでしょうか。 佐竹 スタートダッシュとしては順調だったのですが、いざ始まってみると、活用率がどんどん低下して、約半分になってしまいました。そこで全社アンケートを実施したところ、およそ8割の社員が「全然使っていない」または「週に1,2回程度しか使わない」という残念な回答でした。さらに理由を尋ねると「どこで活用したらいいか分からない」「どんなプロンプトを入力すればいいのか分からない」「そもそもAIで何ができるのか分からない」という答えが並びました。 ―興味関心はあるものの、実際の使い方で戸惑いを感じていたということでしょうか。 佐竹 はい。そのため、活用に向けたオンラインセミナーを実施することにしたんです。全12回実施し、延べ1036名が参加してくれました。セミナーでは、社内で特に「Party on [...]
Slack導入支援事例の紹介 広川株式会社様
Yoshida2025-04-21T15:44:57+09:00オープンコミュニケーションで、創業167年の知見を守る 安政4年創業の広川グループは、「食品」「エネルギー」「住宅設備」「保険」「旅行」など、幅広い分野で、地域の人々の生活を支えてきた。地元顧客やパートナー、メーカーとの連携を大切にしてきた企業にとって、「情報」は蓄積すべき大切な資産。一人一人の社員が持つ「情報」を集積していくツールとしてのSlackを導入に、リバネスナレッジはどう寄り添ったのか。リバネスナレッジの「Slack導入支援サービス」事例第一号となった広川株式会社 常務取締役 廣川充明氏に伺った。 「情報と知見」を会社の財産にしたい ―Slack導入を検討されたきっかけを教えてください。 広川株式会社 廣川 充明氏(以下、廣川) もともと弊社ではセールスフォース(以下 Salesforce)を導入しており、Slackの存在は知っていました。DX化の必要性も認識しており、今後、社内情報をSalesforceに集約していく上で、シナジー効果を最大限発揮できる社内コミュニケーションツールはSlackだという認識もありました。 ただ、導入にはハードルもありました。人的・時間的な意味での導入コスト面もそうですし、導入後ちゃんと使いこなせるのかどうか。また、社内コミュニケーションツールとして利用してきた別のツールから、社員がスムーズに移行することができるのか、データ移動も順調に運ぶかなど、さまざまな懸念事項がありました。 広川株式会社 常務取締役 廣川 充明 氏 ―それでもSlack導入の可能性を探っていらしたと。 廣川 Slackアプリ自体の秀逸さは理解していたからです。膨大で雑多な情報がきちんと整理・蓄積されることに加え、検索力も高い。チャネルもきれいで、ファイルのプレビューもしっかり見られる。特にSlackの持つロジカルシンキング的な構造やシステムが個人的には好きでした。 ―「ロジカルシンキング的な構造やシステム」について、もう少し詳しくお聞かせいただけますか。 廣川 弊社に限らず、日本人のコミュニケーションは、会話や議論がその場の雰囲気で流されがちです。何となくいつものメンバーが集まり、ふわりとした課題感でミーティングを行い、しかし後から振り返ると、結局「誰が、いつ、誰と、何を、どこまで進めるか」が曖昧だった、という具合です。 また、弊社は卸売業や中間流通がメインなので、ルート営業が多いんです。昔からのお付き合いをしている取引先も多く、いわゆる「顧客とどれだけ親密な信頼関係を築けるか」が売り上げに直結します。 そうなると、どうしても社員個人の資質やスキルによるところが大きく、結果的に、限られた社員がその地域のキーパーソンを把握していたり、相手企業の内情を熟知していたりといった状況になりがちです。 ただ問題は、その社員が担当を外れたり、会社を去ったりした場合、その人が持っていた「情報や知見」ももろともに散逸してしまうということです。例えば「10年前まで取引があったあの会社となぜ疎遠になったのか、いまや誰も知らない」ことが起こり得る。 それ以外にも、それぞれの部門が、各部署のフォーマットや入力ルールで資料を作成しており、情報共有や引継ぎがうまくいないケースも散見されていました。そうした課題を一挙に解決してくれる存在が、Slackだったんです。 「何のために導入するか」、世界観のヒアリングからスタート ―Slack導入に逡巡もあった中でリバネスナレッジと出会ったということでしょうか。 廣川 そうです。2023年にSalesforce主催のイベント「Dreamforce(ドリームフォース)」に参加し、そこでリバネスナレッジの代表の吉田さんと取締役の平塚さんに出会いました。 それまでの私は、個人的にはSalesforceのコンセプトや理念には共感しつつも、最終的には「組織文化となじむか」が最大のポイントだと感じていました。 でも、吉田さんの言葉で考えが変わったんです。彼は言いました。「会社の情報資産は、個人がため込むものではなく、会社が蓄積するべきものだ」と。「会社とはチーム運営であり、そこに賛同できないなら、業務委託でもいいはずですよね」という発言は、本当にその通りだなと。 この言葉に背中を押され、数年後に迎える創業170周年の節目までに社内文化と情報蓄積の在り方を刷新したいと考え、Slack導入を決めました。 ―リバネスナレッジに対して「ピンときた」といった感じですね。 廣川 何かを一緒に進めていく相手って、結局「共感できるかどうか」がポイントだと思います。吉田さんの言葉や、がっしりと握手してくれた平塚さんの手が、「この人たちと一緒なら、成し遂げられる」と感じさせてくれたんです。 ―実際にSlack導入に際して、リバネスナレッジからどのような提案がありましたか。 廣川 まずは契約前に、「ゴール地点」を決める話し合いがありました。現状課題をヒアリングして、Slack導入後にどんな結果を得たいか、会社として「どんな世界観をもちたいか」を丁寧に聞き取り、言語化していってくれたんです。この作業はおそらく自分たちだけでは難しかったと思います。 ―ちなみに御社が目指された「世界観」とはどういうものですか。 廣川「オープンなコミュニケーションを目指そう」というものです。 ―裏を返すと、それまではあまり「オープン」ではなかった? 廣川 コミュニケーションはそれなりにありましたが、それでも「失敗」は隠すべきものだし、なるべく怒られたくない心理も働きます。会社からの発信情報も、社員全員が見たのか見ないのか、リアクションが曖昧でした。 「クローズドなコミュニケーション」が多いのも気になっていました。担当者同士は個々にコミュニケーションをとっていましたが、それがオープンな情報として会社全体で共有されていないという状況でした。 ―導入に際しては、リバネスと御社の担当チームが一緒に作業を進めていったのでしょうか。 廣川 ええ、Slack導入担当チームには、なるべく社内文化に染まっておらず、構造的に物事を考えられる人材を集めました。その結果、Slack導入担当窓口は、中途採用、かつSalesforceを使い始めて1年未満という社員になりました。 ―システムに詳しい人選を、あえて避けたのですか。 廣川 SalesforceもSlackもノーコードですから、システムエンジニアでなくても構いません。むしろゴリゴリのシステムエンジニアより、ニュートラルに物事を捉らえられる人選を重視しました。 ―導入後、社内でのアレルギー反応はありましたか。 廣川 ある程度は出ましたが、あくまで想定範囲内でした。リバネスナレッジさんと一緒に、あらかじめ想定質問やクレームを洗い出し、対応策を事前に整えていたおかげです。同時に、Slack導入後は、そのシステムを最も使い倒してもらいたいバックオフィス(総務や経理、人事)を中心に、最初から巻き込む戦略も立てました。 [...]
Slackはインプットのツールではなくアウトプットのツールでありあなたの味方である
Yoshida2024-09-11T16:37:44+09:00Slackの利用方法の話 Slackはチャットツールでしょう? そう思っている人は少なくないのではないでしょうか。もちろんチャットツールではあるのですが、それは機能の一部でしかありません。 今回はそんなSlackを、ユーザー個人としてどのように捉えて活用していくのかという話をしたいと思います 情報浸透の型について これはSlackに限らずなのですが、組織内においてどのように情報が浸透していきますか?という話です 私達はSlackで日々のコミュニケーションを行いながら情報をワークスペースに蓄積するという意識で使っています 一方で、メール文化のようにホワイトリスト形式(情報の受信者を発信者側でコントロールする方法)でのコミュニケーションでは、受信した人は発信された内容を理解していることが求められることが多いのではないでしょうか かつて私達も通ってきた道ですが情報量が増えるにつれて現実的ではなくなりました。 この際に文化として分かれていくのが、メール運用の型は崩さず、受信者をより細かくコントロールする形式になるか、情報の風通しを良くして必要な時に必要な情報にアクセスできるようにするのかという分岐点があります。 情報の受信者を細かくコントロールするようになると、日々のコミュニケーションによりデータサイロが作られることが状態化し、上下の情報の非対称性によって権力勾配が出来てしまうみたいな環境要因を生み出す可能性があります。 Slackを活用することによって、このような非効率なやり方から卒業し、情報統制ではなく情報活用によって組織のイノベーションを促していくという流れが来ているように感じています 閉鎖系から開放系に変わった組織ですべきこと ここでは非常に大きな飛躍が生まれます。閉鎖系で育ってきた人に取っては、受け取れる情報についてはすべて頭に入れなければならないと信じていますから、その文化からの脱却が争点となります Slackで見える情報すべてを頭にいれるというかつての行動を実践すると何が起きるかというと、情報の海に溺れてしまいます そうならないためにどのように意識を変えていくかを考えていきましょう Slackに情報を蓄積していく Slackには日々のコミュニケーションを通して情報が蓄積されていくプラットフォームです。 そのため、利用者には発信を促すことになる訳です 組織内の皆さんの発信が、組織の血となり肉となる。そういうツールです。 発信の促しが成功すると、情報量のカンブリア爆発が起こります 組織内にこんなにも情報があったのかと驚きさえするのではないでしょうか これが組織の筋肉かと、その躍動感に圧倒されてしまう訳です 情報量は日々増加していきますが、これを一人の頭の中にすべて入れることは出来ません。そういうものなのです ここには180度転換するくらいの意識の改革が必要です。一人でそういう意識になっても周りがそうなっていないと孤立してしまいます だからこそ私達のようなSlack導入支援のプロにハンドリングしてもらうということが功を奏します Slackから情報をインプットするのではなく、あなたもSlackに情報をアウトプットしていく。そしてその情報が必要な時に取りに行く事が出来るというのがSlackの真骨頂です。 あなたに必要な情報はこれですか? 少し未来の話をします。 Slackには御存知の通り(?)Slack AIという機能が搭載され、生成AIがユーザーのお世話をしてくれるようになっています。 コンテンツの要約や、まとめ機能によって蓄積された情報が適切な粒度に整えられあなたの手元に届きます もう少し将来の話をすると、AIは今後自律的に働くエージェント方式に変わっていくでしょう 自分が動く前にAIが動いてくれているという状態が確実にやってきます その時代にはより多くの情報があなたの手元に届くようになっていることでしょう。 手を伸ばせば知ることが出来る情報が溢れているのです。 そんな時にAIは提案するようになります。あなたが必要な情報はこれですか?と。 時代は圧倒的に動き出している この激動の時代は、コラボレーションが適切に行われないと乗り越えることは難しい時代だと言えるでしょう Slackを使うことで、人間同士での助け合いが出来るようになった組織も少なくないと思います 今後はそのコラボレーション先にAIも加わってくる、それだけの話しですが、とても大きなインパクトを持つようになるでしょう その日に向けて今できることは、Slackの捉え方を変えていくことです 情報量に溺れるのではなく、情報を蓄積しておくのである 情報に溺れてしまうのは、そこにある情報をすべて頭に入れようとしているからでしょう Slackへの向かい方についてもアップデートし、日々健やかに仕事が行えるように組織もアップデートしていきたいものです。
SlackとSalesforceを連携させる方法:2024年9月ver.
Yoshida2024-10-04T11:01:21+09:00SlackがSalesforceによる買収が完了したのは2021年7月です。すでに3年以上が経過し、SlackとSalesforceの連携にもいくつかの方法が出てきました。 2024年9月時点で利用できるSlack-Salesforce連携について紹介したいと思います SlackをSalesforce連携すると何が嬉しいのか Salesforceは色々なことが実現できるツールで、Webアプリで何でもできてしまうといっても過言ではありません それはそれで便利なのですが、便利故にシンプルに記録を残したいという動機でSalesforceを開くと、全然関係ないデータも目に入り気が散ります そこで、弊社ではSlackアプリを作って簡単に記録が出来るようにするといった、やりたいことによって機能を絞り込んだアプリを作ってSlack上から情報を登録するというような事を行っています。 SlackからのSalesforce連携は、やりたいことをシンプルに・短時間に実現するために利用できると思ってください。 連携方法 ノーコード Slackアプリを使う Salesforceのフローを使う Slackのワークフローを使う Slack Sales Elevateを使う Slackアプリを開発して使う SlackアプリでSalesforceと連携する Salesforce連携にはSalefsorceが提供する純正Slackアプリが便利です 純正アプリを設定することで出来るようになることは2つあります 一つは、Slackのスラッシュコマンドから機能を呼び出すことが出来ます もう一つは、Salesforceのフローからの呼び出しに利用するという使い方になります。これは後述しますが、Salesforce側からプッシュして情報を投稿する際に投稿ユーザーとして使われます。 何が出来るの? Salesforceのレコードを検索する パイプラインを表示する 販売チャンネルを作成 レコードを作成する 組織の管理 Salesforceのフローを使う Salesforceのフローを使ってSlack側にデータを送ることが出来ます。 例えば商談のフェーズが更新された時に、その商談の情報をSlackに投稿したいという場合にフローを使うとノーコードで簡単に情報を送ることができます。 Salesforceのフローのアクションノードの中にSlackに関する設定がありますので、これを使って欲しい機能を実装する形になります。 Slackアクションノード Slackチャンネルをアーカイブ ユーザーがSlackに接続されているかどうかを確認 Slackチャンネルを作成 Slackの会話に関する情報を取得 [...]
Slackの導入で失敗しがちなパターンはどこにあるのか
Yoshida2024-09-30T17:42:25+09:00Slack導入2024年の最新事情についてはこちらをご参照ください 2024年に入り10社程度のSlack導入支援や再起動を行ってきました。今回はこの経験を元に、どのような時にSlack導入が失敗しやすいのかについてお伝えしていきたいと思います。 Slackの導入に失敗するケースは? 電話での問い合わせから抜けられない Slackを導入したにも関わらず、担当者への質問が電話で飛んでしまいというパターン 利用開始当初にSlack上に情報を蓄積するという意識を持たせないとこのパターンに陥ってしまう Slackで質問する事によって情報が蓄積されるというのはその通りなのですが、ここで大事なのが「質問をしてくれる人」です よくある質問については、回答出来る人があらかじめ投稿しておくというのも一つのやり方としてはありますが、質問をしてくれる人が現れた時はぜひたくさんの人からスタンプを付ける等で支援をしてあげるようにしてみてください。質問が良く集まるカルチャーを作っておくことによって、自然とSlack上に知見が蓄積され、検索によって課題が勝手に解決していくという状態に持っていくことができるはずです 情報量が多すぎてSlackを使うのがしんどい Slackの活用が進んでいくとSlack上に蓄積される情報量が自然と増えていきます このタイミングで「しんどい」状態になる組織によく見られるキーワードが「未読管理」です Slackを活用するにあたって未読管理という概念を提唱し始めると黄色信号だと思ってください Slackは元来、すべての情報をしっかり読むというツールではありません。未読状態の情報が存在するのが当たり前なのです すべてを読むことが出来ているというのは、そもそもSlackの活用度合いが低いか、たまたま読む時間が膨大にあったかのいずれかになるでしょう 未読の投稿があるとチャンネル名が太字になるため、それを読まなくてはならないと思いがちではあるのですが、そんな必要はありません 本当に必要なのは「アクティビティ欄」に数字アラートがついていない状態を保つ。これだけです Slackでは所属するチャンネル数は常に増えていってしまいますから、無理せずに使うようにしましょう こちらのテーマについては以下のコンテンツで詳しく書いています。お時間ございましたら御覧ください 潔癖な人ほど #Slack が嫌いになってしまうから プロフィールの設定が適当になっている これも意外とあるあるです。プロフィールの設定が適当になっているという状態 1️⃣ プロフィール画像がデフォルトのまま 意外とありますデフォルトアイコンのまま放置されているユーザー これは組織全体のSlack活用の気力を削ぐ原因になりますので、確実に潰しておきたい要件です 自分の顔写真を設定するのが嫌というパターンは当然あると思いますが、今現在は簡単に写真をイラスト風に加工してくれるようなアプリも存在していますので、写真がどうしても嫌という人にはそういった加工も許可して許容するという使い方にしましょう なぜそれが重要なのかというとSlackにはSlackコネクトという外部のワークスペースとチャンネルを共有する機能があります。これを使うと、社外の人がプロフィールを目にする訳です。円滑なコミュニケーションを考えた時にデフォルトアイコンだと視認性が悪く、そもそも記憶に残りません。ぜひアイコンの設定をお願いします。 デフォルトではないけどアイコンが著作権を犯している場合 これは要注意です。好きなキャラクターのアイコンを使ったりしていませんか?こちらについては社外から見られる可能性がある以上、組織のコンプライアンスどうなってるの?と疑問を持たれる可能性があります。気をつけるようにしてください 2️⃣ 表示名と氏名欄に漢字しか入っていない こちらも意外と多いのですが、漢字のみではなくローマ字表記を入れるようにしましょう。 特におすすめなのが「ローマ字表記 + 漢字」の組み合わせです 私の場合でいうと George YOSHIDA / 吉田 丈治 リバネスCIO といった形です。 これをすることによってメンション効率がとても良くなります。特に最初にローマ字名を置いておくことをおすすめしています @ge くらいまで打つだけでメンション候補に名前が上がります。 もし漢字しか登録されていない場合どうなるかというと @吉田 と書かなくてはならず漢字の変換という手間が発生します。 吉田ならまだマシですが、例えば斎藤や渡辺さんがいた場合はどうでしょうか。 漢字のパターンが多すぎますし絶対にヒットしません。メンションしたいだけなのにめちゃくちゃ時間がかかることは必至です。 そうなっていない場合は是非ご検討ください。コミュニケーション効率が上がりますよ。 まとめ [...]
Slackの導入支援を通してたどり着いた2024年最新情報
Yoshida2024-09-30T17:37:34+09:00Slackが登場してから10年が経ち、Slack AIをはじめとする多くの機能が追加されてきました。当初は主にIT志向の組織で使用されていたSlackですが、現在では幅広いユーザー層に浸透しています。機能の進化に伴い、Slack導入支援の重要性が高まっており、適切なサポートによってスムーズなSlack活用が可能となっています。 → リバネスナレッジのSlack導入支援 日本の組織におけるコミュニケーションの課題 日本の組織の特徴として、クローズドなコミュニケーションが多いことが挙げられます。いわゆる「縦割り組織」はその典型例で、コミュニケーションにかけた時間(コスト)が効果的に再利用されていないのが現状です。Slackを導入してコミュニケーションチャネルを統一することで、このコストを組織の資産として活用するための動きが広がっています。 オープンなコミュニケーションの重要性 Slack上でのコミュニケーションにおいて、DMの利用が多くなりがちですが、これは公開された情報ではないためSlackの検索結果には現れず、コミュニケーションコストの回収が難しくなります。2024年以降のビジネスシーンでは、いかにオープンなコミュニケーションを実現するかが組織の重要な課題となっています。 Slack AIと情報の蓄積 Slackは過去のチャットログを検索し再利用できるよう設計されてきました。2024年には、この検索機能が生成AIによってさらに進化を遂げています。Slackで蓄積された情報をもとにRAG(Retrieval-Augmented Generation)を実現し、生成AIが最適な情報をアウトプットする方向に進んでいます。 情報蓄積の課題と解決策 Slack AIの活用は、蓄積された情報が多い組織ほど効果を発揮します。しかし、過去のやり取りの正確性や、情報を誰が証明するのかという課題があります。また、情報蓄積にはコストがかかるため、経験の浅い社員が担当することも多く、これが将来的な組織の負債となる可能性があります。 新しいコミュニケーション手法 Slack導入支援を通じて、以下のようなコミュニケーション手法にたどり着きました: 情報は生データで蓄積する(例えば録音/録画データ) サマリーは人間ではなく、AIが行う(文字起こし&議事録変換) 人間は情報に自分が考えていた意図を付与する役割を担う 事実の蓄積はAIが行い、個人の意図や所感を付加して蓄積する これらの方法により、必要十分な情報をバイアスなく蓄積することが可能になります。 生成AIとの協働 現時点で、生成AIとの効果的な協働方法を描けている組織は多くありません。しかし、生成AI活用は人間の時間効率を劇的に向上させ、組織に正確な情報を蓄積するための鍵となるでしょう。 詳細をこちらで語っています 当テーマについては、SFUG CUP2024にて準優勝を獲得しています リバネスナレッジのSlack導入支援 リバネスナレッジでは、2015年からSlackを利用し始め、数々のSlackアプリを提供してきた経験があります。この豊富な経験を活かし、Slack導入支援プランとして提供しています。 最新のコミュニケーション手法を取り入れ、組織の生産性を向上させたい方は、ぜひリバネスナレッジにお問い合わせください。私たちの経験と知識が、皆様の組織変革をサポートいたします。 → Slack導入・活用支援サービス 後日追記:「Slack導入の失敗につながる落とし穴」を追加しました
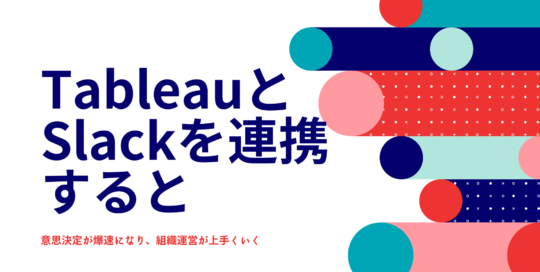
データドリブンはもう古い!?TableauとSlackでアクションドリブン組織へ
Yoshida2022-05-13T18:44:48+09:00TableauとSlackを組み合わせることで、意思決定を加速し、アクションにつなげるコミュニケーションを生み出すことが出来るという事例です。 リバネスでは、あらゆるデータをSalesforce上に格納しています。Salesforceに格納されたデータをTableauを使って可視化するという使い方をしています。 データドリブン組織(経営)とはなにか その名の通り、データを元にした意思決定をする組織です。と、一口に言っても、何をデータとして格納していくのかは組織によっても変わってきますし、効果的なデータが取れているかどうかを判断し、日々改善していくといった運用の工夫も必要になってきます。 Salesforceを使っていると、日々の最新情報や、経時変化(事例:Salesforceはスナップショットを使いこなしましょう 参照)の情報を簡単に見ることが出来ます。Salesforceからも具体的にダッシュボード例が紹介されていますので、興味があればこちらをご覧ください。「営業の見える化」 に役立つダッシュボード6選 これらのダッシュボードを整備し、定期的に確認をしながら、その後のアクションについての意思決定を行う。そのあたりがデータドリブン経営のとっつきやすい入り口になります。 データドリブンの成れの果て 私自身(吉田丈治)もそうですが、ダッシュボードを作り始めると、データを色々な角度から分析して見たくなります。ダッシュボードには様々なデータが紐付けられ、ボタンクリックでフィルターがかかりグラフが動的に変化する。様々な分析をすることが出来るゴージャスなダッシュボードがいつしか出来上がる、そんな経験がある人がいるのではないでしょうか。 凝ったダッシュボードを作ることで生まれるのは、情報の齟齬です。人によって何を見て何を得るのかが一意にならなくなってしまいます。情報が複雑化すればするほど色々な解釈が出来るようになっていき、一つの方向を向かせるためのダッシュボードではなくなっていきます。 ダッシュボードを分解せよ このような状態になってきた場合におすすめしているのは、ダッシュボードの分解です。 ある特定のタイミングで必要な情報というのはそんなに多くないと個人的には思っています。 例えば、マネージャーが商談の状況を確認する場合を想像して下さい。今必要なのは、部下に檄を飛ばす必要があるかどうかの判断材料です。 ダッシュボードを開くと、あらゆる情報がきれいにまとまった豪華なダッシュボードが出てきますが、必要な情報はそのダッシュボードの中のほんの一部でしかありません。オーバースペックなダッシュボードは開くのに時間がかかり、日々のオペレーションで少しずつストレスが溜まっていきます。 こんな風になってはいないでしょうか?データドリブンがうまく走ってくると、段々と特定のタイミングで必要な情報がなにかが分かってきます。 リバネスではこうなったタイミングで情報を分解していきました。特定の部門のマネージャーが自分の部門の売上推移を知りたいのであれば、その部分だけ切り出した情報を提供することができれば、最小単位で最大効率の情報伝達が可能になります。 最小単位で最大効率の情報伝達 データドリブンの究極系は、一度最大化したダッシュボードを局所最適に分解する事だと言いました。 ここからは、情報伝達からアクションに移す流れを最短距離に縮めていく手法について書きたいと思います。 リバネスではコミュニケーションの中心はSlackを使っています。Slackを使って組織を、人を動かすのが今回のゴールです。 Slackの課題は何でしょうか。それは情報量が多すぎることです。必要な情報から些細な情報まで多くの情報が飛び交います。その為、情報の伝達効率という意味では薄くなりがちなのですが、そこで活躍するのがTableauです。 Tableauでビジュアライズしたダッシュボードはこのように画像として配信が出来ます。 画像をSlackに配信することで何が良いかというと、一瞬で必要な情報が頭に入ることだといえます。忙しく、情報があふれる毎日の中において、情報の取得コストを如何に下げていくのかを考えることで、より効果的な組織運営が出来るようになると言っても過言ではありません。 画像からアクションへ これはあくまでも画像です。Tableauの画面のようにクリックしてフィルタが効くというような使い方は出来ません。しかし、だからこそ一意に情報を伝えることが可能になります。 一意な情報が伝達すると何が起きるかというと、アクションが始まります。Slackに流れた情報を元に意思決定が即座になされ、関係者に指示が飛ぶように変わっていきます。打ち合わせの時間をあえて取る必要もなく、何をすべきかが決定されて実行されるようになります。 これこそがアクションドリブン経営だと私が個人的に考えています。 アクションを忘れないために とは言え、Slackはメンションした会話がそのまま忘れ去られれてしまうことが少なくありません。 これを解決するためのアプリケーションを作りました。それはまた別の実績でお話したいと思います。
Slackでタスク管理をするには
Yoshida2022-08-19T11:09:32+09:00Slackを使っていると、チャンネルのタイムラインの中で様々な情報が行き交います。単純に目を通しておけば良い内容から、自分がアクションをしなくてはいけない情報まで、様々です。Slackを使いこなし、組織の規模が増えていけば行くほど、メッセージの数は増大し、自分に宛てられたメッセージについて検討する時間が増えていきます。 Slackで送られたタスクは忘れがち 一つや2つなら問題ないタスク管理も、数が増えてくることでだんだんと忘れてしまいます。Slackにはデフォルトで「メンション&リアクション」や「スレッド」という機能が備わっているのですが、これはあくまでも情報の羅列であって情報の整理には向きません。数が少ないうちはすべて見ることができますが、量が増えてくるとこの画面を見るのがつらくなってきます。スレッドは新しい投稿が加わると上に上がってくるのですが、タスクを終えて一言加えると最新情報としてあがってきます。つまり、未対応のpostが埋もれていってしまうのです。これがなかなかつらい。特にモバイルを使っていると顕著に辛くなってしまいます。 だったら解決済みのスレッドはアーカイブできればいいじゃないか、そう思ったときに作ったのがTASUKARU-TaskAll-というアプリケーションです。 メンションを羅列し、用済みになったスレッドはアーカイブしていく。それだけで必要な情報だけが残っていきます。シンプル。 最もシンプルな使い方はこれです。これだけで自分に何が残っているのかが把握できるようになります。 ToDo管理もSlackでしたい メンションの管理だけでなく、ToDo管理もSlackでしたいと思ったことはありませんか。私はあります。詳しい話はこちらで書いたので読んでもらうと詳細がわかるのですが、Slackで誰かにToDoを渡したい、自分のToDoも管理したいと言うときに使える機能です。 先程の画像にToDoボタンがあると思うのですが、これを押すと、今現在抱えているタスクリストが表示されます。 タスクの割当は、メッセージ内に .todo もしくは to.do という文字列を含めるだけ。含めた状態でpostをすると、スレッドにアプリが介入し、ToDoを立ち上げてくれます。 ToDoには担当者・締切日・進捗率・アサインした人・タグを設定する事ができます。これらを使って管理していくという使い方です。 リバネスではタスクの受け渡しには基本的にこれを使うことにしています。口頭やslackでメンションしただけというものはタスクをお願いしたことにはならないという認識を全員がもつことが重要。(もちろん一瞬で終わるようなものについてはこの限りではないのですが) 以上のような形で、カスタムアプリを作ることでSlackの利用環境を向上させることができました。 スライドにある通り、インストールして使っていただけますので、是非ご活用ください。 リンクはこちら ・TASUKARUについて ・インストールはこちらから 事例に戻る Slackを使っていると、チャンネルのタイムラインの中で様々な情報が行き交います。単純に目を通しておけば良い内容から、自分がアクションをしなくてはいけない情報まで、様々です。Slackを使いこなし、組織の規模が増えていけば行くほど、メッセージの数は増大し、自分に宛てられたメッセージについて検討する時間が増えていきます。 Slackで送られたタスクは忘れがち 一つや2つなら問題ないタスク管理も、数が増えてくることでだんだんと忘れてしまいます。Slackにはデフォルトで「メンション&リアクション」や「スレッド」という機能が備わっているのですが、これはあくまでも情報の羅列であって情報の整理には向きません。数が少ないうちはすべて見ることができますが、量が増えてくるとこの画面を見るのがつらくなってきます。スレッドは新しい投稿が加わると上に上がってくるのですが、タスクを終えて一言加えると最新情報としてあがってきます。つまり、未対応のpostが埋もれていってしまうのです。これがなかなかつらい。特にモバイルを使っていると顕著に辛くなってしまいます。 だったら解決済みのスレッドはアーカイブできればいいじゃないか、そう思ったときに作ったのがTASUKARU-TaskAll-というアプリケーションです。 メンションを羅列し、用済みになったスレッドはアーカイブしていく。それだけで必要な情報だけが残っていきます。シンプル。 最もシンプルな使い方はこれです。これだけで自分に何が残っているのかが把握できるようになります。 ToDo管理もSlackでしたい メンションの管理だけでなく、ToDo管理もSlackでしたいと思ったことはありませんか。私はあります。詳しい話はこちらで書いたので読んでもらうと詳細がわかるのですが、Slackで誰かにToDoを渡したい、自分のToDoも管理したいと言うときに使える機能です。 先程の画像にToDoボタンがあると思うのですが、これを押すと、今現在抱えているタスクリストが表示されます。 タスクの割当は、メッセージ内に .todo もしくは to.do という文字列を含めるだけ。含めた状態でpostをすると、スレッドにアプリが介入し、ToDoを立ち上げてくれます。 ToDoには担当者・締切日・進捗率・アサインした人・タグを設定する事ができます。これらを使って管理していくという使い方です。 リバネスではタスクの受け渡しには基本的にこれを使うことにしています。口頭やslackでメンションしただけというものはタスクをお願いしたことにはならないという認識を全員がもつことが重要。(もちろん一瞬で終わるようなものについてはこの限りではないのですが) 以上のような形で、カスタムアプリを作ることでSlackの利用環境を向上させることができました。 スライドにある通り、インストールして使っていただけますので、是非ご活用ください。 リンクはこちら ・TASUKARUについて ・インストールはこちらから 事例に戻る
Slackを使って、組織全体の姿を捉える
Yoshida2025-02-04T17:50:15+09:00提供中のアプリについてのご紹介です。 TimeLine for Slack。詳細はこちら 組織全体が見えづらくなってきた 在宅ワークや人数や拠点数の増加によって組織全体が見えづらくなってしまっていませんか。SlackはDigital HQであると宣言し、私たちもかねがね同意しているのですが、オフィス勤務時と決定的に違うことが一つだけあります。それが行き過ぎた最適化です。 オフィスに出勤していると顔が見える範囲のことはなんとなく察しが付きます。表情が見えたり、声が聞こえてくるというなんとなく漂っている情報がインプットされることで、人間はたくさんの情報を得ていると言えます。(一方でそれがノイズで集中できないというパターンもあります) リモートワークでは当然こういったセンサーを働かせることは出来ません。Slackを使いこなしていて、チャンネルが細分化していけば行くほど、リモートワークで他のチャンネルで何が起きているのかを目にする機会がなくなっていきます。 一つのチャンネルに全ての投稿を流すアプリ TimeLine for Slack そこで作ったのがこちらのアプリケーションです。アプリをインストールして設定をすると、全ての公開チャンネルに投稿されたメッセージが一つのチャンネルに流れます。パソコン版のSlackアプリを使っている場合は、分割ビューにタイムラインチャンネルを設定しておくことで、どこで誰がどんなことをしているのかが目に入るようになります。 オフィスに出勤していれば「小耳に挟む」ことが出来たような情報のやり取りが、Slack上にTimeLineチャンネルを作ることで実現することができるのではないか?という提案アプリになっています。 < 事例へ戻る